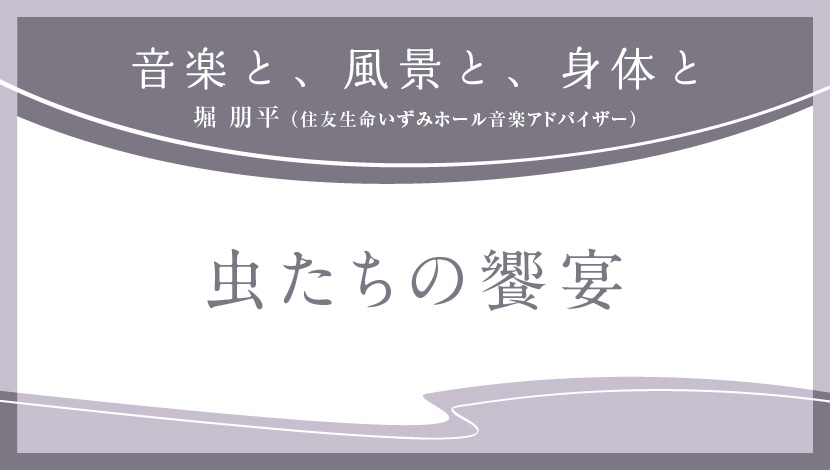
音楽と、風景と、身体と「虫たちの饗宴」
2021.09.14 エッセイ 堀朋平エッセイ 堀 朋平
このエッセイ、気楽に見えてじつは難物。800字の原稿なんて楽曲解説の類でしか経験のない者は、「さぁ自由にどうぞ」と言われると、途端に自分の空っぽさを思い知らされるわけです。この第190号も、まっ白のワードファイルを前に何時間うんうん唸ったことでしょう。なのでいっそ、この呻吟は一体どういう訳なのか、考えてみました。
一人の作曲家にのめり込むと、その作曲家の視線で世界を見てしまうようになります。「愛」とか「神」とか「成熟」といった掴みがたい概念も、その人が経験した(であろう)限りにおいて、初めて腑に落ちる。つまり概念を自分のものにできる気がする。音楽理論のややこしいワードも、あの音楽に当てはめてみて、ようやく理解できる。思えばこれは芸術のあり方にも似ています。風景画は、まずは人間の心情を宿すものとして発展しました(だから純粋な風景を思い浮かべるのはひどく難しい)。音楽から作者の人となりや成立事情などを切り離すのは困難だという認識は、20 世紀以降も根強く共有されています(よって、絶対音楽はあくまで理念にとどまるのでしょう)。
人間は何かに自分を憑依させる傾向がある。学者も、特定の音楽や作曲家に憑依することで初めて受肉した(=身体を得た)感覚を得られる。語られる対象も、誰かに宿られてこそ精彩を帯びてくるのではないでしょうか。特殊で特異なひとりひとりの営みが、そのつど音楽の意味を輝かせるのです。歴史(history)を語ることは、つまり個々人の物語(story)なのだというテーゼは、だから深い。音楽ホールも、何かに憑依した特殊な虫たちがうようよ――この季節だとりんりん――共存できる空間であるとよい、そんなふうに思います。
とすれば、自由なエッセイの書き手とは、憑依すべき宿主を失った哀れな虫に等しい!? いえいえ、今号の私だって結局は「憑依すること」に憑依して書いているのだと思いいたって安心しました。そういえば田園交響曲の第 2 楽章には、暖かな土中でうごめく昆虫たちが聴こえてきませんか。ベートーヴェンはそんな説明していませんけど。
ジュピター190号掲載記事(2021年9月14日発行)
関連記事はこちら
音楽と、風景と、身体と「新時代の散歩」
音楽と、風景と、身体と「傷(トラウマ)と音楽」
音楽と、風景と、身体と「くりかえす日本の夏」
プロフィール
堀 朋平
住友生命いずみホール音楽アドバイザー。国立音楽大学ほか講師。東京大学大学院博 士後期課程修了。博士(文学)。近刊『わが友、シューベルト』(アルテスパブリッ シング、2023 年)。著書『〈フランツ・シューベルト〉の誕生――喪失と再生のオデ ュッセイ』(法政大学出版局、2016 年)、共著『バッハ キーワード事典』(春秋 社、2012 年)、訳書ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト』(アルテスパブリッシ ング、2017 年)、共訳書バドゥーラ=スコダ『新版 モーツァルト――演奏法と解 釈』(音楽之友社、2016 年)、ボンズ『ベートーヴェン症候群』(春秋社、2022 年)など。
公式twitter



