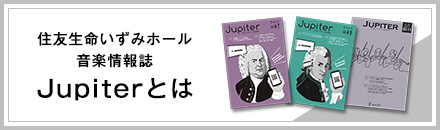文楽の音楽的魅力を味わえる『阿古屋』を、クラシック音楽ホールで
2025.08.07 インタビュー 逢坂 聖也
箏奏者・片岡リサがプロデュースする邦楽シリーズ『和のいずみ』。第3回は"文楽"をテーマに贈る。本公演の大きな聴きどころとなるのが桐竹勘十郎(人形)、豊竹呂勢太夫(太夫)、豊澤富助(三味線)という当代きっての名人を迎えた『壇浦兜軍記 阿古屋琴責の段』より。その魅力について、片岡リサ、豊澤富助に聞いた。
音楽ホールで聴く文楽
──片岡さんは『和のいずみ』が始まった当時から"ぜひ文楽を"とおっしゃっていました。また今回は豊澤さんがクラシック音楽のホールで古典作品を弾く、数少ない機会でもあります。まずはそのあたりのお話からうかがいたいと思います。
片岡:私自身が大阪の出身ですし、やはり邦楽に携わる者として大阪の文化遺産である文楽は必ず紹介したいと思っていました。この公演で初めて文楽に興味を持った方が、ぜひ文楽劇場に足を運んでくれるような公演にしたいと思い、私からも豊澤さんに相談させていただいて実現した企画です。『阿古屋』では私自身もお箏で共演させていただきますので、よろしくお願いいたします。
豊澤:新作をやるような場合を除いて箏曲の方と一緒に弾くというのは、文楽ではいわばタブーなんです。箏や胡弓などもすべて三味線弾きが賄うのが文楽ですから。けれども今回はクラシック音楽ホールでの公演ということで普段とは別枠。それなら喜んでやらせていただきましょうということでお引き受けしました。いずみホールは非常に音が響きます。片岡さんが太夫との息の合わせ方などどんな風に取り扱われるか、楽しみにしています。
音楽の魅力が詰まった『阿古屋』
──その『阿古屋琴責の段』ですが、人形が箏と三味線と胡弓を弾く有名な場面があるとうかがいました。
豊澤:もちろん仕草ですけどね。うまくやりますよ。お箏を弾く時は指もちゃんと動きます。というのが、それ専用の指があるんですよね。指というか手が。そして三味線を弾くところでは、ばちを持たなきゃなきゃいけないでしょ。これもばちを持った手があるんです。それをあるタイミングで人形遣いがすっと入れ替える。
片岡:箏を弾く場面で阿古屋が、爪を付ける前に指をなめる仕草をするんです。さりげないけどこれは実際に箏を弾く人なら実によくわかる仕草で、そのリアルな動きを初めて見た時は、はっとするような驚きがありました。
豊澤:源氏方の重忠が、阿古屋が彼女の恋人で平家の残党である景清の行方を知っているか、知らないかを詮議するわけです。それで遊女ならば責め立てるよりも、箏、三味線、胡弓を弾かせてみろ、その音色でわかると。
──人形の動きや楽器の音色、情感豊かな筋運びなど文楽の魅力が詰まったような場面ですね。
豊澤:文楽の魅力はほかにもたくさんあるんですよ。しかしその昔、まだ洋楽が入ってくるより前には、文楽は「音曲の司※1」と言われていました。ですからこのお話はそういった文楽の、音楽的なところを感じていただける作品と言えるかも知れません。
正しく受け継ぎ、正しく弾く
──その文楽の音楽的な部分を大きく担っているのが三味線の音色のように思われます。豊澤さんが演奏に際して大切にされていることなどはありますか。
豊澤:私達がお稽古の時からよく言われるのが、曲を弾くのではなくて模様を弾け、ということなんです。模様というのはつまり状況、情景、心情。例えば『仮名手本忠臣蔵』の九段目、『山科閑居の段』では、チン、テン、チン、テンという冒頭の4つの音で、雪がはらはらと降っているのを表現しなさいと言われるんですね。たくさん降っているのではなく、ほんの少し舞っているように。これは難しいです。だから常にそういうことを気にかけながら弾いてみる。音質や、間合い、強さを考えて弾きましょうということですね。
──人形の動きと合わせるところにも、難しさがあるのでは?
豊澤:私達は人形の動きなんて見てませんよ。合わせようとも思ってません。「合う」ものなんです、正しくやれば。正しく伝承して正しくやれば必ず合う。合わなければ誰かがまずい。だから正しくやりましょうということです。若い頃に稽古で怒られて、舞台で経験を積んで「合って」いくものなんです。そうすると、こう入れば必ずこう出てくれるっていうのが「息」でわかるようになってくる。数を数えるのじゃなくて、自分の「息」で。数値で表せないのが伝承ですから。
──今、豊澤さんから伝承というお話がありましたが、片岡さんはいかがでしょう。お箏の世界にも共通するような部分はありますか。
片岡:西洋の音楽のように、楽譜ありきではないというところが似ていると思います。お箏でも古典の曲では、例えば「だんだんゆっくり」というところを「少徐」としか書いていないので、それがどういう風なテンポかというようなことはまず先生に教えていただいて、理解して、体に染み込ませて覚えていくわけです。それから自分なりの表現を磨いてゆく。これは文楽と箏曲というよりも、日本の伝統音楽に共通する点だと思います。
豊澤:日本の音楽はもともとは何々検校※2さん、というところが始まりですから。それで楽譜を必要としなかったんです。西洋の音楽ではまず楽譜があって、それを見て忠実に演奏しましょうというのが基本でしょ?でも、そもそも邦楽は楽譜自体がありませんでした。伝承があって、覚え書きみたいなものは目の見える人があとから書き残していく。そういったものだったんです。だから私達文楽の三味線弾きも楽譜は見ないんですよ。
文楽界の重鎮を迎えたスペシャル版
──今回の公演で初めて文楽に触れるという方もいらっしゃると思います。そうしたお客さまに、どんな風に感じてもらいたいと思いますか。
豊澤:単純に曲を楽しんでいただきたいということですね。1つ言えるとすれば、最近はビジュアル重視の世の中ですからどうしても人形に注目が集まりがちですが、本来、文楽は義太夫節が主人公です。太夫が語る、その語りの芸術と申しますか、それが中心です。だからそこがまずいと全部がくずれてしまう。どんなに美しい人形が出てきてもそうは見えなくなってしまう。その点、今回は豊竹呂勢太夫ですから、うまいですよ。そういったことをこれをきっかけにおわかりいただけるとうれしいですね。
片岡:第1回は尺八の藤原道山さん、第2回は津軽三味線の上妻宏光さんをメインゲストに迎えて、それぞれに素晴らしい演奏をお届けすることができました。その中にあって、今回は文楽界の重鎮の方々をお招きするという『和のいずみ』スペシャル版とも言える内容。ぜひ多くのお客さまにお運びいただいて、文楽の魅力に触れていただきたいと思います。
※1 日本の近代以前における音楽、または音楽を用いた芸能を「音曲」と呼び、司は専門職、一番上の人を意味する
※2 室町時代以降の視覚障がいを持った人の官職の最高位。音楽や鍼灸などの職能を極め、社会的に活躍した。
壇浦兜軍記 阿古屋琴責の段 あらすじ
平家の滅亡後、鎌倉方の武将畠山重忠は、平家の侍大将であった悪七兵衛景清の行方を追っている。景清の愛人、阿古屋を拷問にかけるが、白状をしない。そこで、箏・三味線・胡弓の三曲を演奏させて、音色の乱れの有無で、景清の行方を知っているかどうかを探ろうとする。
ジュピター213号掲載記事(2025年7月10日発行)
プロフィール
Tomisuke Toyozawa
豊澤富助
昭和46年16歳で文楽協会三味線部研究生となる。師は二代野澤勝太郎、野澤勝司と名のる。昭和47年には自由契約となり、国立劇場で初舞台。昭和48年高校卒業と同時に文楽協会技芸員となる。昭和59年五代豊澤富助と改名する。平成18年度文化庁国際交流使に指名される。平成元年芸術選奨文部大臣新人賞、平成26年外務大臣表彰、平成28年度大阪文化祭賞優秀賞、令和元年度大阪文化祭賞〈第1部門〉団体賞、第43回(令和5年度)国立劇場文楽賞優秀賞など多数受賞。
プロフィール
Lisa Kataoka
片岡リサ
大阪音楽大学卒業、大阪大学大学院文学研究科博士前期課程修了(音楽学)、同大学院博士課程単位取得満期退学。第21回 出光音楽賞、平成13年度文化庁芸術祭〈音楽部門〉新人賞。皇太子殿下・秋篠宮殿下御前演奏をはじめ、2012年 大阪市「咲くやこの花賞」、平成22年度 大阪文化祭賞、平成31年度文化庁芸術祭優秀賞など、多数受賞。伝統音楽の枠を超えた音楽性が、様々なジャンルで高く評価されている。 現在、大阪音楽大学特任教授、同志社女子大学・兵庫教育大学非常勤講師。宮城社師範。
公式HPプロフィール
Seiya Osaka
逢坂聖也
大阪芸術大学卒業後、大手情報誌に勤務。映画を皮切りに音楽、演劇などの記事の執筆、配信を行う。2010年頃からクラシック音楽を中心とした執筆活動を開始。現在はフリーランスとして「音楽の友」「ぴあ」「関西音楽新聞」などのメディアに執筆するほか、ホールや各種演奏団体の会報誌に寄稿している。豊中市在住。
関連公演情報
- 片岡リサ プロデュース 新・日本の響き
和のいずみ 第3回 - 8/30(土)16:00開演
【曲目】
玉岡検校 : 鶴の声
山根明季子 : 委嘱新作
「壇浦兜軍記 阿古屋琴責の段」より ほか
【料金】
一般 ¥5,000 U-30 ¥2,000 フレンズ特別価格 ¥4,000
公演に関する詳細情報は、ホームページでご確認ください。