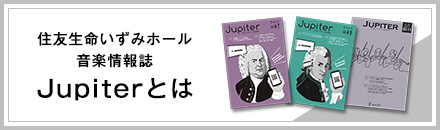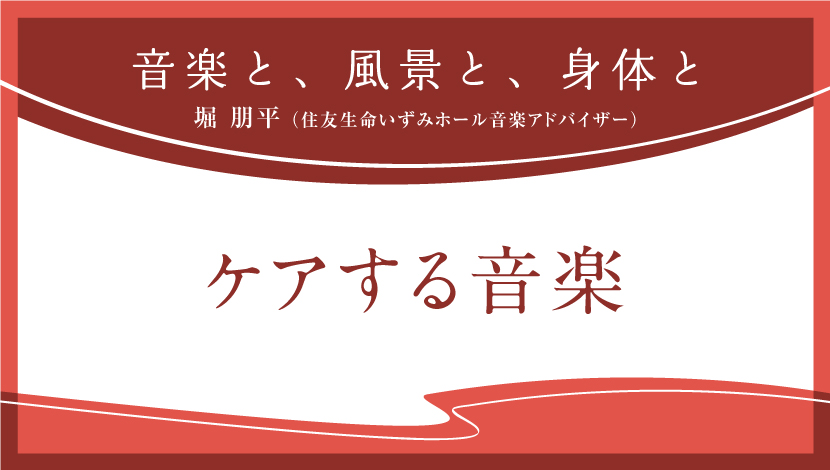
音楽と、風景と、身体と「ケアする音楽」
2025.11.21 堀朋平エッセイ 堀 朋平
ケアする音楽
たまには俗っぽいゼニの話から入るのをお許しください。
去る6月に「サントリー音楽賞」を受賞された山田和樹さんのスピーチによれば、同賞の賞金は、ある年にふとしたきっかけで2倍になったのだとか。数年まえに和樹さんがマーラー・シリーズの功績で受賞された「芸術選奨」の賞金は、そのおよそ10分の1。これは金額が大きく上がった昨年度からの数字で、たとえば作曲家の全集楽譜が揃うくらいのありがたい額でした。さらに「京都賞」というのがあり、その賞金は「サントリー音楽賞」よりさらに一つ桁が上。すべて公開されている数字ですので、ご興味がおありの向きはググってみてください。
ところで「京都賞」を受けた人は、世界レベルで大きな影響を与えた文化人ばかり。音楽分野ではJ.ケージやN.アーノンクールやP.ブーレーズといったレジェンドが名を連ねています。先ごろ「思想・倫理分野」で贈賞されたフェミニズム思想家キャロル・ギリガン(1937-)の功績は、半世紀まえから「ケア」の思想を説いてきたこと。ケアとは、困っている人やマイノリティの視線で、解決しがたい問題をねばり強く考え続けていく倫理のこと。効率や利益を重んじる社会では忘れられがちなことですが、昨今の日本でも、文学や映画やアニメや漫画の分析から、あるいはケアラーの実態調査から、この思想がいかに大切かということが説かれています。「鎧で体を覆う」ような生き方ではなく、いわば自己にたくさんの孔をうがち、周りの声に限りなく開かれた「多孔的」な生き方を見直そう、というのが趣旨です。
音楽でいえば、この対比は「ベートーヴェンvs.シューベルト」にも重なります。古くて新しいテーマでしょう。ロマン派には概して「多孔的」な人が多い。ケアをめぐる思想書が、とくに19世紀イギリス文学を専門とする研究者から澎湃として興っているのも、むべなるかな(小川公代さんの『ケアする惑星』がお勧めです)。そういえばシューベルト中期の《美しき水車小屋の娘》(1823)では、主人公は意固地にわが道をつらぬきましたが、晩年の《冬の旅》(1827/8)では、はずれ者に心を開いていきます——犬とかカラスとか物言わぬ老人とか、やすやすと答えをくれない存在に。年を重ねるにしたがって、人には「ケア」の思想が染みてくるのかもしれません。
ジュピター215号掲載記事(2025年11月13日発行)
プロフィール
Tomohei Hori
堀 朋平
住友生命いずみホール音楽アドバイザー。国立音楽大学・九州大学ほか非常勤講師。東京大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。『わが友、シューベルト』(アルテスパブリッシング、2023年)で令和5年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(評論部門)受賞。著書『〈フランツ・シューベルト〉の誕生――喪失と再生のオデュッセイ』(法政大学出版局、2016年)、共著『バッハ キーワード事典』(春秋社、2012年)、訳書ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト』(アルテスパブリッシング、2017年)、共訳書バドゥーラ=スコダ『新版 モーツァルト――演奏法と解釈』(音楽之友社、2016年)、ボンズ『ベートーヴェン症候群』(春秋社、2022年)など。やわらかな音楽研究をこころざしている。
公式X