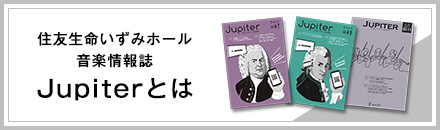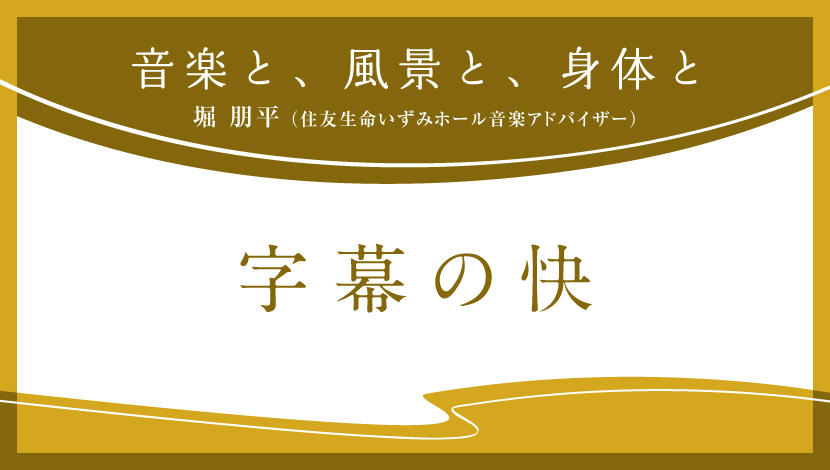
音楽と、風景と、身体と「字幕の快」
2025.07.18 エッセイ 堀朋平エッセイ
字幕の快
外国語の歌詞を対訳で手元に広げるのと、大きな電光文字で日本語だけが浮かぶのを眺めるのと、皆さまはどちらがお好みでしょうか?「対訳」は、客席のわずかな灯かりで小さな文字を追うので目はしょぼしょぼするけれど、じっくり浸れてあとに残る。いっぽうの「字幕」は、単語ごとの深いニュアンスまでは掴めないけれど、とにかく見やすくて楽ちん。どちらも長所と短所がありそうです。字幕公演のあと「歌詞も配ってほしかった」という声を、複数のお客様から直接いただいたこともありました。できれば「どちらも」ほしくなるものかもしれませんね。
最近は、当ホールの公演のために字幕を制作する機会が増えています。作る側からすれば、対訳と字幕はまるでちがうもの。対訳は「あとに残る」ための正確さが何より重視されます。対する字幕は、アーティストと同じ“場”=ステージに浮かんでは消えるスリリングなせりふ。いわば歌い手による「ふきだし」にも等しいものではないでしょうか。同じ歌詞が繰り返されるばあいを比べてみましょう。対訳 では、歌詞の反復を(基本的には)訳し直しませんが、字幕では繰り返しをどうパラフレーズするかが大事になります。なにせ同じ内容がわざわざ再び語られるのですから、ふさわしいエモーショナルなことばにしたくなります。「わたしのもつれた歌は 夢からの呼び声のよう」という歌詞であれば、「そう、わたしの歌は呼び声なの 遠い夢からの──」のように。
これは、青年メンデルスゾーンの姉ファニーが書いた歌曲《夜のさすらい人》の一節。7月25日に、彼女の内面世界をたどるレクチャー&コンサート「アンナとファニー その“声”を聴く」が開かれます。松井亜希さん&阪田知樹さんとともに、葛藤と憧れがこもった女性作曲家の“ことば”を字幕で味わうひととき。「快こそが活動を完全にする」とは、かの大哲学者アリストテレスの言葉です(『ニコマコス倫理学』)。アーティストの「ふきだし」を作ってステージに浮かび上がらせる仕事は、一介の学者にとって大いなる快であり、音楽活動を完全にしてくれる体験にほかなりません。
ジュピター213号掲載記事(2025年7月10日発行)
プロフィール
Tomohei Hori
堀 朋平
住友生命いずみホール音楽アドバイザー。国立音楽大学・九州大学ほか非常勤講師。東京大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。『わが友、シューベルト』(アルテスパブリッシング、2023年)で令和5年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(評論部門)受賞。著書『〈フランツ・シューベルト〉の誕生――喪失と再生のオデュッセイ』(法政大学出版局、2016年)、共著『バッハ キーワード事典』(春秋社、2012年)、訳書ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト』(アルテスパブリッシング、2017年)、共訳書バドゥーラ=スコダ『新版 モーツァルト――演奏法と解釈』(音楽之友社、2016年)、ボンズ『ベートーヴェン症候群』(春秋社、2022年)など。やわらかな音楽研究をこころざしている。
公式X