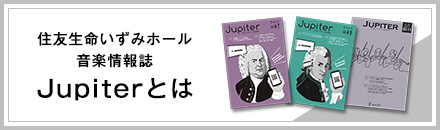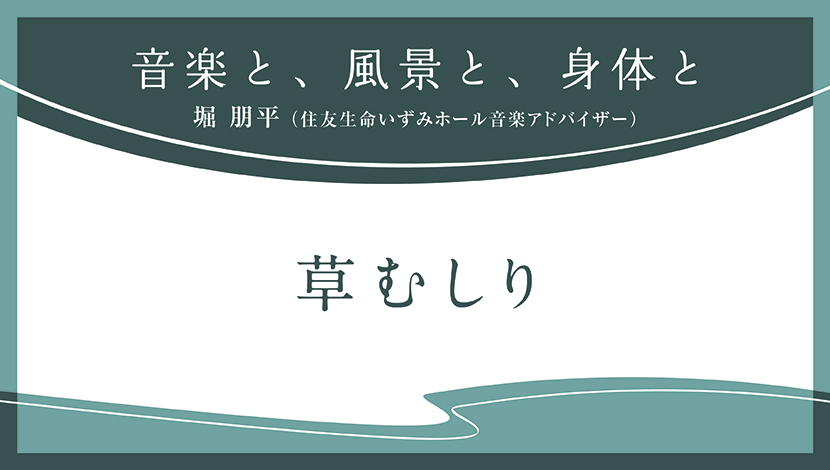
音楽と、風景と、身体と「草むしり」
2024.07.23 エッセイ 堀朋平エッセイ 堀 朋平
草むしり
やたら群れたがる植生と、じめっとした見かけ、妙なツヤと奥ゆきのある深緑……どく矯め(毒をなおす)に由来するという説もあるそうですが、やっぱり薬草というより雑草にみえるので真っ先に標的となります。若いうちはあんがいスルッといかないので、少し育ったヤツからやっつけたほうがよい。
どんなに暑くても、長袖タオル軍手の完全防備をお忘れなく。虫さされ対策もさることながら、草や虫のエキスが首すじやら袖の中につかぬように、です。貴重な野草を選り分ける注意も欠かせません。おもえば庭師なるものは、主人の好みをよく知る味わい深い存在だったはず。女庭師サンドリーナが小鳩に託したメロディ(K.196)とか、でも《美しき水車小屋の娘》の庭師はいまひとつ存在感ないんだよな、とか……陽ざしのなかでぼんやり思い浮かべながら。
気がつくと草たちの残骸は2山、3山と積みあがっている。ちょっとした田舎にある実家で、今年はずいぶん汗を流しています。家の中でも、床やドアや壁などをゴシゴシやっている。身体を、とりわけ手を動かすとき人は自分の内にある“過剰”を追い散らしているのだといいますが※──たしかに。手の自動運動に身をゆだねる、その脳内にあったのは何かと問われれば、昨冬におだやかな旅立ちをした父が湯あみしてもらっている姿(湯灌というそうです)。草をむしる私の手は、心の中で亡き父を湯あみさせていたのです。
生前にはめんどくさがって洗いたがらなかった愛車も、実家に帰るたびに水をかけて雑巾で拭きたくなる。ほんの20分の仕事です。その夜は父が車を洗っている(←奇跡!)夢をみた、なんて母は言います。
触覚とは「内部にはいりこむ」特別な感覚なのだと力説する哲学者が18世紀に現れました※※。視覚や聴覚とちがって触覚の刺激は“心”の扉をひらくのかもしれません。日ごろ思っているよりもずっと深く、直接に。その体験は、ときに現実を大きく超えた──現実にはもう叶わぬ──出会いをも可能にするのでしょう。皆さまもこの夏、草たちと戯れてみてはいかがでしょうか?
※D.リーダー『HANDS―手の精神史』松本卓也・牧瀬英幹訳(左右社、2020年)
※※伊藤亜紗『手の倫理』(講談社、2020年)
ジュピター207号掲載記事(2024年7月10日発行)※掲載記事に一部加筆、修正を加えています。
プロフィール
Tomohei Hori
堀 朋平
住友生命いずみホール音楽アドバイザー。国立音楽大学・九州大学ほか非常勤講師。東京大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。『わが友、シューベルト』(アルテスパブリッシング、2023年)で令和5年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(評論部門)受賞。著書『〈フランツ・シューベルト〉の誕生――喪失と再生のオデュッセイ』(法政大学出版局、2016年)、共著『バッハ キーワード事典』(春秋社、2012年)、訳書ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト』(アルテスパブリッシング、2017年)、共訳書バドゥーラ=スコダ『新版 モーツァルト――演奏法と解釈』(音楽之友社、2016年)、ボンズ『ベートーヴェン症候群』(春秋社、2022年)など。やわらかな音楽研究をこころざしている。
公式X